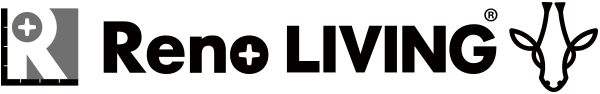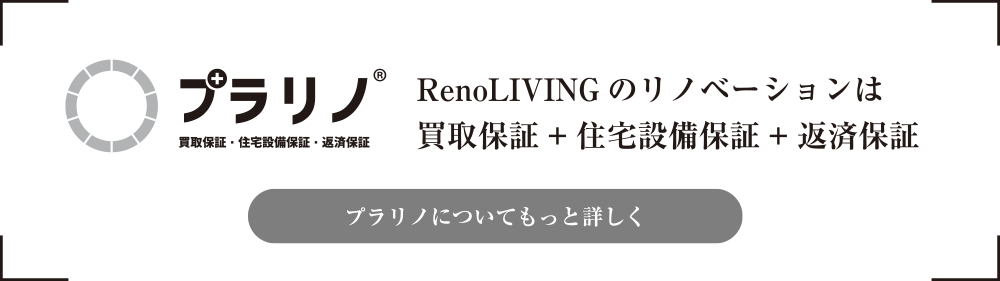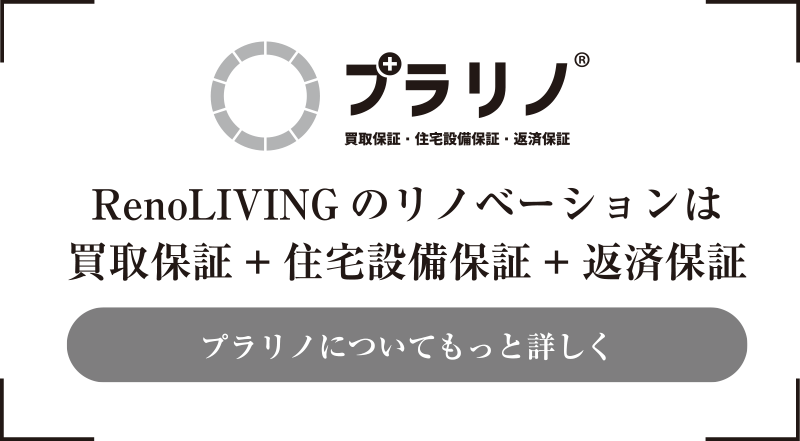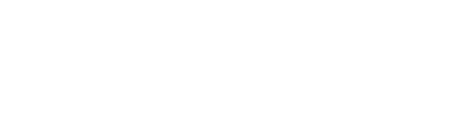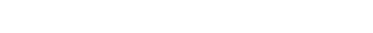【必須】実家の相続登記「前」にすべき準備とは。
2024.10.17
こんにちは!リノリビングです。
今回は、「相続登記前にすべき準備」のお話です。
親や祖父母が住んでいた家。
売却したり、リノベーションをして住替えたり、または賃貸物件として貸し出したり…
多様な活用方法がありますが、その前に「相続登記」という手続きをしなくてはなりません。
2024年4月から義務化された、この相続登記。
手続きする前に、準備が必要です。
大変ではありますが、放置していると罰金を科される危険性があります。
今回は、そんな「相続登記」についてと、
「相続登記前にすべき準備」について、詳しくお届けします。
1:【基礎知識】まずは、相続登記について知ろう。
【疑問1】相続登記って一体なに?
相続登記とは、
「あたらしい所有者に、名義変更をする手続き」のことです。
2024年4月から義務化されており、 3年以内に手続きしないと、罰金を科されることがあります。
【疑問2】相続登記が必要な理由とは。
相続登記が必要な理由は、「相続登記をしないと、家を処分できない」ためです。
相続した家を工事したり、売却したくても、 その家の所有者でないと、手を加えることはできません。
すでに亡くなっている親や、祖父母が所有者である時は、
相続登記をして、家を処分する本人の名義に変更しなくてはなりません。
2:【実践】相続登記前にしなければならない準備4選。
相続登記をする前に、以下の4つの準備を行います。
【準備①】登記簿で、所有者を確認する。
【準備②】相続人は誰か、調べる。
【準備③】遺言書があるか、調べる。
【準備④】必要に応じて、遺産相続協議書を作る。
1つずつ、説明します。
【準備①】登記簿で、所有者を確認する。
親や、祖父母の家を相続することになったら、
まずは、その家の「登記簿」を取得して、家の所有者を確認しましょう。
登記簿は、現在では「登記事項証明書」と言われており、 法務局などで取得することができます。
【疑問】登記簿のどこを見れば、所有者がわかる?
登記簿は、「表題部」と「権利部」の2つに分かれています。
「権利部」の、「甲区」と呼ばれる部分に、現在の所有者が記録されています。
所有者が亡くなっている時は、相続登記をしなくてはなりません。
【準備②】相続人は誰か、調べる。
所有者が亡くなっている時は、血縁者を調べて、 自分の他にも「相続人」がいるか確認しましょう。
相続人は、亡くなった所有者の子ども、親、兄弟、孫などが該当します。
子どもがいれば、子どもが相続人に。
子どもが亡くなっていれば、孫が相続人に・・・というように、相続する権利は引き継がれていきます。
所有者の「履歴事項全部証明書」を取得すれば、 自分の他にも相続人がいるか、確認することができます。
【疑問】なぜ、相続人全員と連絡を取るのか。
自分の他にも相続人がいるのに、連絡がとれていない場合は、 相続登記をすることができません。
なぜなら、相続登記には、相続人全員の登記簿や書類が必要だからです。
必ず他の相続人に連絡をとり、家を相続する権利があることを伝えましょう。
【注意】放置していると、相続人が増えてしまう。
相続登記を放置していると、相続人はどんどん増えていきます。
たとえば、曾祖父母が家の所有者なら、
曾祖父母や祖父母の子どもたち、つまり「またいとこ全員」が相続人となります。
この場合、相続人の数は数十名と、とても多くなってしまいます。
相続人がたくさんいると、連絡をとるだけでも大変ですので、 早めに確認しておきましょう。
【準備③】遺言書があるか、調べる。
亡くなった所有者が、相続の方法を記した遺言書を残していないか、確認しましょう。
遺言書の多くは、所有者が、手元で保管しています。
しかし、法務局や、「公証役場」という施設で保管されていることもあります。
所有者の手元に遺言書がなくても、法務局や、公証役場にないか確認しておきましょう。
【注意】遺言書は、勝手に開封してはいけない。
亡くなった人の手元にある遺言書は、家庭裁判所で「検認」という手続きが必要です。
特に、封をしてあるものは、家庭裁判所で開封しなければなりません。
開封してしまうと、罰金を科される可能性があります。
また、遺言書は、書き方が法律で決められています。
要件を満たさない遺言書は、家庭裁判所にて「無効」と判断されます。
遺言書が、家や亡くなった人の手元にあった場合は、封を開けずに家庭裁判所で手続きしましょう。
【ポイント】遺言書の内容に納得できない時は、交渉できる。
相続人1人だけにすべてを相続させるなど、遺言書の内容が不公平だったときは、
自分の相続分を請求したり、訴訟をすることもできます。
この場合、相続人の間で遺産分割協議をすることになります。
トラブルに発展しやすいので、弁護士に相談することをお勧めします。
【準備④】必要に応じて、遺産相続協議書を作る。
「自分の他にも相続人がいて、遺言書がない」
「遺言書が無効だった」
そんな時は、 「遺産相続協議書」を作りましょう。
【疑問1】遺産相続協議書とは。
遺産相続協議書は、 相続財産の分け方に「相続人全員が同意したこと」を証明する書類です。
相続人全員の署名と実印が必要です。
【疑問2】どんな時に、遺産相続協議書が必要なのか。
以下の3つ全て当てはまるときは、相続登記に、遺産相続協議書が必要です。
・相続する遺産に、家などの不動産がある。
・相続人が、2人以上いる。
・遺言書がない。
遺言書通りに家を相続する時や、
自分しか相続する人がいない時は、遺産分割協議書は必要ありません。
【ポイント】遺産相続協議書は、家のことだけ書けばOK
相続登記するための「遺産相続協議書」は、法務局に提出します。
家など、不動産の相続のことが記述してあれば、受理されます。
株式や預金など、不動産以外の資産については、必要ありません。
ただし、銀行や税務署、自治体に提出するときにも、遺産分割協議書が必要です。
こちらは、不動産以外の資産も全て記述する必要がありますので、ご注意ください。
【まとめ】家を相続することになったら、すぐに相続登記の準備を始めよう。
今回は、相続登記に関する知識と、「相続登記前にすべき準備」についてお話ししました。
家の相続登記をせずに放置しておくと、 書類や手続きがどんどん増大していきます。
相続登記をしないままでいることには、リスクしかありません。
家を相続することになったら、すぐに相続登記の準備に取り掛かりましょう。